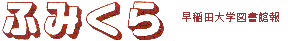 No.12(1987.10.26)p 3-4 No.12(1987.10.26)p 3-4明治期資料マイクロ化事業に着手 ―62年4月事業委員会発足 最近、紙の劣化が大きな社会問題として取り上げられ、酸性紙による印刷文化崩壊の危機が叫ばれている。酸性紙によって作られている印刷資料の寿命は、約100年間しかないといわれているが、わが国において酸性紙の原因といわれる木材パルプの生産が始められたのが明治中期であり、まさに問題の100年を経過しようとしている。このことは、わが国近代化の経緯を示す基本的な印刷資料が崩壊の危機に瀕していることを意味する。国立国会図書館等の調査によっても、明治初期及び中期の印刷資料の劣化が激しく、緊急な処置を要することが明らかである。(図書館研究シリーズ№24)外国においては早くからこの問題が取り上げられ、この課題に対処するためのいくつかのプロジェクトが進められている。 また、市場に出回っている明治期の資料は数が少なくなってきており、従って、価格が上昇し一種の貴重書扱いとなっている。すなわち、図書館をはじめとする各機関が現在所蔵している明治期資料に代りうるものは、入手がきわめて困難な状況にあり、この状況は今後とも悪化の一途をたどることが予測されるのである。 明治時代は長い日本歴史のなかでも、特別の意味をもつ転換期であり、明治時代を抜きにして日本の歴史は語れない。ヨーロッパの歴史のなかで、19世紀という時代が特に重要な意味を持っているように、わが国の歴史のうえで特に重要な意味をもつ明治時代の印刷資料が紙の劣化等によって消滅しようとしている現在、これらの資料を何らかの方法によって保存し後世に伝える責任が現代に生きるわれわれに課せられている。 早稲田大学図書館は、幸い戦災及び震災を免れ、明治期資料を保有する図書館としては、国立国会図書館等と並んで日本有数の図書館の一つである。その意味で早稲田大学図書館は明治期資料を保存し後世に伝えるという大きな責任の一端を担っているのである。 明治期に刊行された資料の総数は不明であり、また、当時は出版社が地方に多く存在していたことを考えると、明治期資料は日本全国に分散所蔵されているものと思われる。その結果、例えば早稲田大学図書館及び国立国会図書館に所蔵されているもののみで、明治期資料を網羅することは到底出来ない。したがって、このプロジェクトの遂行には非常に難しい問題点が内包されていることはいうまでもない。しかし、敢えて早稲田大学が現時点でこのプロジェクトを企画するのは、前述の酸性紙問題及び明治期資料の稀少性から考えて、この課題が緊急に対応しなければならないものであり、かつ、その責任を果すという意味においても、将来このプロジェクトが全国的なものとして成長し、外国におけるSTC、ESTC、およびNSTCと肩を並べるまでに成長する日が必ずや来るであろうことを信じてこのマイクロ化事業に着手した。今後何かと困難にいきあたることもあろうが、教職員各位のご協力を切にお願いする次第である。
昭和62年4月~
図書館ホームページへ Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||