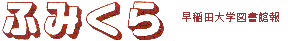 No.19(1989.9.1)p 3 No.19(1989.9.1)p 3
中村義人(和書データベース化事業室担当調査役)
情報の量的な増大、利用者の要求の多様化、目録情報提供の迅速化に対応するため、当館では、すでに昭和60年度以降の図書整理については、システム化され、コンピュータ端末のオンラインによる検索がはじめられている。しかしシステム化以前の目録検索は、依然としてカード目録のみに頼らざるを得ないのが現状である。利用者はカード目録と、オンライン目録の併用という煩わしさを背負うことになる。この不便さを解消させなければならないことは、館全体の大きな課題である。また、簡略な情報のみしか伝えられないカード目録と違い、様々な検索の可能なオンライン目録の便利さを知ると、それを近年分のみではなく、すべての所蔵資料にまで広げられれば、利用者へのサービス、レファレンス、そして将来への蔵書設計にも非常な進展がみられるだろうと夢は広がる。ところが、遡及入力の対象となる図書の冊数は膨大であり、それに伴う莫大な費用、人材の確保が必要とされ、途中での後退が許されないだけに、ただちに遡及入力作業に踏み入ることはできないでいた。 しかし昨年5月に、紀伊国屋書店と和書の遡及入力について「ジョイント・ベンチャー方式」によって実施するとの奥島館長の構想が打ち出された。早速、館内で検討が開始され、紀伊国屋書店側担当者を交えたワーキンググループも結成され、20人からなるメンバーが慎重に討議をかさね、その結果が課長会に提出され、以下の項目について決定をみたのである。 1.遡及入力の範囲(対象) 2.入力作業方法 3.入力図書の年代順位 4.入力項目 5.典拠 6.人事体制 以上の4.5.については、作業内容・入力基準の解説にゆずるとして、1.2.3.6.については以下の通りである。 1.入力対象 本館に所蔵されている和漢書約74万冊のうち、当面は次のものを除外して入力する。 (1)特別図書および準特別図書(約6万2千冊) (2)別置和装本(含漢籍)(約12万5千冊) (3)中国語図書(約2万8千冊) (4)朝鮮語図書(約5千冊) (以上約22万冊を除くと入力対象は、52万冊) 2.入力作業方法
3.入力図書の年代順位 遡及入力作業は、新しい年代の図書の情報をより早く利用者に提供したいという方針もあり、まず Japan MARC にヒットするものの多い年代からはじめることとし、次の順位で作業を進める。
4.人事体制 本事業を遂行するにあたり、紀伊国屋書店との作業分担は、紀伊国屋書店側で、 (Ⅰ) 入力担当者約25名を採用する。 (Ⅱ) その入力者をまとめ、作業の統括を行う専従者を情報制作部より3名出す。 (Ⅲ) 図書運搬等に必要な要員も適宜採用する。早稲田大学側が担当するのは、 (1) 入力データの最終チェック並びに、目録作成に必要な司書としての専門知識を紀伊国屋書店側に指導する。 (2) 進行状況のチェックと、事業全般の運営方針を紀伊国屋書店側と協議しながら作案する。 (3) 入力図書の搬入搬出の立会い。 以上の項目のうち、(3)については閲覧課が担当するが、(1)(2)の業務についての専従者は4名とし、館長直属の独立した組織とする。 (なお、作業場所は大学構内に場所を用意し、専用端末28台も早稲田側で提供する。) 以上が、和書データベース化事業の骨子であり、今年の1月までの準備、テスト期間を経たのち、2月2日より、本作業を開始した。 まず、入力順序に従って学習図書室所蔵図書約4万冊について入力を開始した。この作業には、まだ入力開始当初で様々な問題点の解決が必要であったこと、また予定しなかった請求記号変更、再装備作業も入り、意外に手間取ったが、ほどなく完了する見込みであり、いよいよ7月中旬には本館書庫の52万冊に挑戦することになる。 当時業では精度の高いデータを作成することがなによりも重要と考えているが、それと同時に一日の処理冊数をいかに伸ばすかも大事な点である。両者の兼合いをいかに調整していくか、紀伊国屋書店と共に、今後努力していかなければならない。 当面の目標は、新図書館オープン時(1991年4月)までに、昭和44年以降の約16万冊について遡及入力、現行 WINE へのロードを完了させ、その他新館の学生用開架図書(当初約8万冊)レファレンス室用図書の入力、ロードが完了できればまず成功と考えている。 当初の構想は、遡及対象の52万冊を3年半の1992年8月までに完成させることにあるが、開館以来100年余の歴史を持ち、幾多の先人達が収集、整理してきた図書を、ほとんど再整理という形で、一貫した件名、分類等を付与するという、思いきった事業だけに、これからも難問が続出するであろう。将来的には各学部所蔵の図書数10万冊に、慶応以前の国書10万余冊にまで遡及事業が進んで行けばと考えている。 本事業完成後には、質の高い、詳細な書誌情報がデータベース化され、学生研究者に大きく貢献することが期待される。また、この事業は、早稲田大学の遡及入力ということのみに留まらず、他大学の遡及入力等にも利用されるような、データベースセンターへの発展も考えられるのである。そこには単なるデータだけではなく、早稲田大学図書館が大きな知的資源としてその姿を現わし、眠っていた資料を誰かが起こして新しいインパクトを現代に与えるようなことも期待できるであろう。 図書館ホームページへ Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |
