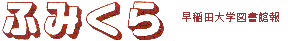 No.21(1989.12.5)p 3 No.21(1989.12.5)p 3『壷碑』の思い出
木村時夫(社会学科部教授) 明治期の刊行物など所有することの少ない私には、それについて語る資格などない。それでもつい先日、長らく私の書架にあった、栗本鋤雲の『匏菴十種』と、福地源一郎の『幕府衰亡論』(いずれも初版本)とを友人に献呈した。再びひもとくこともないであろうと思ったし、その友人がそれに関心をもち、またそれを懇望していたからである。 しかし私の日本歴史研究は幕末維新史から出発したのである。復員後の私は日本の敗戦の衝撃からであったが、「日本軍国主義の研究」をテーマに、旧制大学院に入り、煙山専太郎先生の御指導を受けた。テーマがテーマだけに、手をつけかねていた私に、先生は「和歌山藩の津田出の兵制改革を調べてみたらどうか」といわれた。当時の私には津田出とは全く未知の人物であったが、先生はそのヨーロッパ留学中、ベルリンにおいて、津田の縁戚にあたる松波仁一郎氏から、津田の事績について聞いておられ、その細かい調査を私に指示されたようである。 先生はまず図書館から『南紀徳川史』の該当部分数冊を借り出されて私に貸与された。私はそれを読むうちに、津田に『壷碑』という自伝のあることと、堀内信という旧和歌山藩士に『晦結溢言』という和歌山藩の兵制改革に関する著作のあることを知った。 その後先生は岡本柳之助の『風雲回顧録』や文明協会編の『近世文化史上に於ける大隈重信候』の中に、津田に関する言及があるといわれ、その両冊を送って下さった。私はそれによって津田の事績の輪郭をほぼ知ることができた。しかしそれだけにいよいよ、津田自身の手になる自伝『壷碑』を一読したく、熱心にそれを探した。図書館にはなく、国会図書館にもなかった。一日私は足を棒にして神保町の古書店を一軒一軒尋ね歩き、水道橋にまで足をのばしたがそれはなかった。 探し始めてから2年後、『晦結溢言』(明治40年刊)だけは駿河台下の明治堂の書架の中から発見した。その時の喜びはたとえようもなく、今もそれを忘れることはできない。 『壷碑」の方はついにみつけることはできなかったが、当時東大の史料におられた林幹弥氏が、その筆写本が「史料」にあると知らせてくれたので、早速「史料」に赴いた。幸い所員の吉田常吉氏の厚意で数日間の借覧を許された。コピー機のような便利なもののなかった時代であるから、私はそれをノートに筆写した。しかしその喜びはたとえようもなかった。津田出の研究を手がけてから実に3年後であった。『壷碑』にはこの筆写本を贈丁した刊本が出ているらしいのであるが、それは未だに手にしていない。すでに40年の余をへた今日ではあるが、もしそれを今日手にすることができるなら、万金を惜しまぬつもりである。 それはともかく、津田の明治2年の和歌山藩における徴兵制の施行は画期的なもので、明治5年以降の徴兵制の基礎ともなった。明治政府の津田によせる期待も非常に大きく、『大久保利通日記』や『木戸孝允日記』の中にも関連史料を発見することができた。 灯台下暗しというか、『大隈伯昔日譚』の中にも津田に関する重要な記述があった。それは西郷から津田の政府への起用を求められた大隈が、それほどの人物でないことを語ったところである。 晩年の津田に対しては、前記『晦結溢言』の著者堀内にも非難の記述があるが、津田に対する曲解にもとづくものである。 それはともかく、私は津田の研究から始まり、さらに山川浩の『京都守護職始末』によって触発され、幕末維新への関心を深めたのであって、当時のことを思うと、『壷碑』の探書の思い出に連なるのである。 図書館ホームページへ Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |