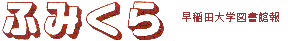 No.21(1989.12.5)p.13-15 No.21(1989.12.5)p.13-15
マイクロ化作業内容(その2)
加藤絢子(明治期資料マイクロ化事業室)
3.書誌情報点検
現在マイクロ化している明治期図書は、全て書庫に納めてあるものなので、既に整理済みのものです。しかし、明治・大正期に書かれた書誌データは記述内容が簡略で、現在の利用者の要求に応えるにはどうしても再整理が必要です。また早稲田大学図書館では、伝統的に著者よりも書名を重視し書名カードだけを作ってきました。明治時代の書名・著者名の読み方については参考にする資料も乏しく、読み方を確定することは大変難しい作業です。紅野敏郎先生、弥吉光長先生にお聞きしながら、仕事を進めています。本の著者は著名な方々ばかりではありません。明治時代の役場の人名録や紳士録等ルビのついた資料をご存知の方がおられましたら是非お知らせ下さい。
4.保存情報の記録
書誌を点検しなおすと同時に、本がどんな状態になっているのか、紙はどのように変化しているのかも調べて記録します。これが保存情報の記録です。英国図書館をはじめ数館の方法を参考にさせていただき、図のような表にまとめました。この表の項目をチェックするだけでなく、場合によっては、「釘を抜いて糸綴じに変えた」というような情報もメモしておきます。各項目をチェックしてみますと劣化や変色の度合いの項について検討の余地があるようです。100年も経た紙に「変化なし」ということはまずあり得ませんし、1冊全部が同じ状態ではない場合など判断に迷うことがあります。この記録は次に保存計画を考え、実行する時の資料となるものですから、現在確認した時点での劣化緊急度によるABC
のランクをつけておいた方が、今後の作業に便利かもしれないという気がしています。まだまだ改良すべき点があると思いますので、お気付きの方はお教えいただきたいと思っています。
| チェック |
保存情報 |
月日 |
|
| |
装丁 |
|
和 |
|
洋 |
|
帙入 |
| |
紙の種類 |
|
和 |
|
洋 |
| |
原装丁のまま |
|
| |
再製本したもの |
|
| |
破損箇所 |
|
背 |
|
表紙 |
| |
|
|
全体 |
|
その他 |
| |
修復の要あり |
|
綴じ |
|
破損 |
| 紙の劣化の度合い |
|
Excellent |
非常に良好 |
| |
Good |
しなやかで、折り曲げても簡単に折り目がつかない |
| |
Fair |
折り曲げると折り目はつくが、切れてしまうことはない |
| |
Brittle |
折り曲げると切れてしまう |
| |
Very brittle |
くずれかかっている |
| 変色の度合い |
|
変化なし |
| |
中程度までの変色 |
| |
はなはだしい変色 |
| |
|
虫害あり |
その他 |
| マイクロ化に伴う処置 |
|
保存情報記録カード。実際はカードの両面に印刷されています。
5.図書のクリーニング
長い間書庫におかれた本は、ゴミや埃で大変汚れています。それで本を1ページずつ刷毛で払いクリーニングをします。クリーニングをすることにより、欠けたページや乱丁・落丁も見つかります。大変手間がかかりますが、4名の学生アルバイトの方々にお願いしてこの作業を続けています。クリーニングした本は見違える程きれいになり、フィルムの鮮明度も増します。
6.解体・補修
クリーニングすると同時に折れた頁や皺になった頁はアイロンで延ばし、少しの破損は軽く修理しておきます。綴じてある釘が錆びてボロボロになっているような場合は、釘を抜いて糸で綴じておきます。そのまま放っておくと錆が広がり、紙が破れてしまうからです。しかしなるべ現在の姿のままで残すことを大前提にし、決して大幅な補修は行わないように心掛けています。手をかけたがために本をダメにした例が大変多いと聞いているので、原装保存を方針としています。釘できっちり止まっている開きの悪い本(再製本した本に多い)や厚さが5~6cm
もある百科事典のような本は、撮影時に無理をして本を傷めないように、あらかじめ綴じを切って撮影者に渡します。常に同じ人がフィルム撮影していますので、こちらの希望もよく分かり、トラブルもなく進行しています。
7.点検及び保存箱作製
撮影が終了し戻ってきた本について、再び痛み具合をチェックし、場合によっては再製本に出します。撮影後の本の扱いについてはCAP
編集長の木部徹氏のご指導で保存箱を作製し、1冊1冊を箱に納めて書庫に返却しています。箱形、バインダー形の2種類でクリーム色のボード(弱アルカリ性
pH8.5 厚さ1㎜ 防カビ処理済)を使用しています。手作り作業ですので大変手間がかかりますが、保存方式が確立し次のステップへと行動が起せる時期まで本を埃から守り、酸化を少しでも遅らせ、本の寿命を長らえさせるようにと念じ、1箱1箱作製しています。箱の背にタイトル、マイクロフィッシュナンバー、請求記号を記入し、その本が撮影済みとわかるようにしています。
8.協力依頼
作業内容(その1)(その2)で記した手続きに従って、毎日作業は続けられています。しかし最も大切で重要な仕事は、協力してくださる図書館を増やしてゆくことです。現物調査の段階でタイトルページや奥付の無い本、再製本した時点で裁断を深くしすぎてページ付あたりまで切りこんでしまった本、多巻物でその中の1冊が欠けてしまった本等々が見つかった場合には、どこかで完全な本を探し出し、出版された当時の姿を再現する必要があります。また早稲田大学に所蔵している冊数は全出版物の一部分にすぎないのですから、本学に所蔵していない本を一緒にマイクロ化してゆきましょうということを話し、協力をお願いしなければなりません。幸い東京女子大学や筑波大学からは欠けている部分を拝借することが出来ましたし、慶應義塾大学には相互協力の一環としてご協力いただいております。近々、慶應義塾大学所蔵本だけのユニットができる予定です。国立国会図書館や近代文学館にも協力をお願いしています。東京近辺にない本を所蔵しておられる可能性の大きい東北・関西・九州地区の図書館が、明治を残す仕事に共に加わって下さるようにお願いしたいと思います。 |
 |
本のあれこれ
再整理中にこんな本を見つけました。
残香集 宇井叟明編 明治11年8月序(へ5-5699)
花翁一貞追善のために子宇井叟明が編集した俳句集の4丁裏にローマ字俳句が載っています。英人ゼームスがローマ字で書いた俳句にカタカナでルビがふってあります。
「アメアヒヤモノニタユマスナクカハツ」
「サハルモノナクテミラルルサクラカナ」
よく見て下さい。1句目と2句目とのよみが入れかわっています。ともに17字なので、丁度うまくルビかふれたのでしょう。
また「ma」を「メ」と読んでいます。正しくは「アマアヒヤ」となります。
本文中どこを見ても正誤表もことわり書きもありません。皆こんなものかと眺めていたのでしょうか。
「ふみくら」本号の表紙に使用した『天地有情』をマイクロ化する際にも、異版本で訂正箇所の有無を調べるために、アルファベットが大変役にたちました。明治時代の刻工や植字工はアルファベットに慣れていなかったのでしょう。pをqにしたり、eとaとを間違えている本を、版を重ねる時に訂正した箇所が多くあります。これによって、改版本かただ刷り直しただけの本なのかを判断する手がかりにしたことがよくあります。 |
 |
今でこそ多くの人が英語に親しんでいますが、100年前にはいったい何人の人がこの俳句をローマ字で読めたことでしょう。
なお、英人ゼームスとはゼームス坂の地名で知られている第二代明治丸船長J.M.James
ではないかと思われます。
図書館ホームページへ
Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved.
Archived Web, 2002
>
|
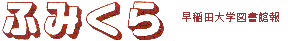 No.21(1989.12.5)p.13-15
No.21(1989.12.5)p.13-15

