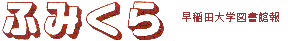 No.25(1990.10.15)p 11 No.25(1990.10.15)p 11
噴婭埳崙壆彂揦忣曬惂嶌晹 榓彂僨乕僞儀乕僗壽挿 嶐擭2寧傛傝奐巒偟偨擖椡嶌嬈偼堦擭敿傪宱夁偟丄7寧枛傑偱偵15枩審傪姰椆偟偨丅憗戝杮娰偺柧帯婜埲崀偵庴偗擖傟偨榓恾彂栺52枩嶜偑杮帠嬈寁夋偺懳徾偱偁傝丄偙傟偱3妱庛偺擖椡傪廔偊偨偙偲偵側傞丅嶐擭偺棫偪忋偑傝帪婜偼寧娫暯嬒3,000審偱偁偭偨偑丄弨旛婜娫傪宱偰彊乆偵儁乕僗傾僢僾偟丄尰嵼傑偱偱寧娫暯嬒8,330審偺婰榐偲側偭偰偄傞丅J/MARC懳徾暘乮1969擭埲崀偺庴擖恾彂乯偺擖椡張棟偼崱擭6寧偱姰椆偟丄7寧偐傜偼愴屻乣1968擭偺J/MARC偑側偄帪戙偺恾彂偺擖椡傪奐巒偟偨偑丄偙傟偐傜偺擖椡偼僆儕僕僫儖擖椡偑傎偲傫偳偱偁傝丄崱傑偱偺僸僢僩丒僇僞儘僊儞僌傪庡偲偟偨擖椡宱尡偲栚榐抦幆偑帋偝傟傞乽戞擇抜奒乿偵擖偭偰偒偨丅 尰嵼丄婭埳殸壆彂揦懁偺恖堳懱惂偼擖椡幰25柤丄愱廬幰4柤偱偁傝丄嶐擭偺摉帪嬈奐巒埲棃悢柤偺戅怑幰偼偄偨傕偺偺丄懡偔偑偙偺帠嬈偵堄媊傪擣傔偰嶲壛偟懕偗偰偔傟偰偄傞丅摉弶偼栚榐枹宱尡偺擖椡幰偑僨乕僞僔乕僩側偟偱偳偺掱搙怣棅偺偁傞僨乕僞傪擖椡偱偒傞偺偐憗戝懁偵偛怱攝傪偍偐偗偟偨偑丄奺恖偺岦忋怱丄愊嬌揑側嶲壛堄梸偑惉壥偵寢傃偮偒丄暘椶丒審柤傕娷傔偰奺擖椡幰偑僨乕僞僔乕僩側偟偱捈愙僆儞儔僀儞擖椡偡傞偙偲偵惉岟偟偰偄傞丅偙偺攚宨偵偼憗戝愱廬幰偺曽乆偺挌擩側偛巜摫偲WINE僔僗僥儉偺婡擻偺慺惏傜偟偝偑偁傞偙偲傪朰傟偰偼側傜側偄丅 傑偨丄変乆傕怴恖偺擖椡幰偵懳偡傞嫵堢懱惂偺妋棫丄擖椡幰偺悢乆偺宱尡傪惙傝崬傫偩乽擖椡儅僯儏傾儖乿傗乽帠椺廤乿偺姰惉偵傛傝慡堳偺栚榐抦幆岦忋傪恾偭偰偙傟偵偍墳偊偟偰偒偨丅傑偨丄幚嵺偺擖椡嶌嬈偱偼慡懱傪4斍偵暘偗偰嫤椡懱惂傪偲傞偲偄偆岺晇傪峴偭偰偒偰偄傞丅堦恖堦恖偑彊乆偵棫攈側丣僆儞儔僀儞僇僞儘僈乕"乮変乆偺娫偱偼僆儞儔僀儞偵傛傞栚榐嶌惉幰偲偄偆堄枴偱擖椡幰傪偙偆屇傫偱偄傞乯偵側傝偮偮偁傝丄偙傟傜偺擖椡幰偺拞偐傜崱擭2柤偑暷崙OCLC傊攈尛偝傟CJK偺擖椡僾儘僕僃僋僩偵嶲壛偡傞傛偆偵側偭偨偙偲傕変乆偵柌傪梌偊偰偔傟偨丅 偝偰丄憗戝偲婭埳崙壆彂揦偲偼偙偺慿媦帠嬈偺奐巒帪傛傝僨乕僞儀乕僗僙儞僞乕峔憐傪寁夋偟偰偒偰偍傝丄崱夞慿媦帠嬈偑婳摴偵忔偭偨偲偙傠偱僙儞僞乕壔傊岦偗偰嬶懱揑側妶摦撪梕偵偮偄偰偺摙媍偑峴傢傟偨丅偦偺寢壥丄怴帠嬈偲偟偰憗戝偲婭埳殸壆彂揦偲偑嫤椡偟偰憗戝偺怴婯庴擖榓恾彂偺擖椡傪峴偆偙偲偑寛掕偟偨丅慿媦僨乕僞偲摨條丄惛搙偺崅偄僨乕僞偑怴姧杮偵偮偄偰傕憗偄帪婜偵岞奐偱偒傞傛偆弨旛傪恑傔傞偙偲偵側偭偨丅傑偨丄婭埳崙壆彂揦懁偵愝抲偝傟偰偄偨WINE抂枛婡傕廬棃偺10戜偐傜26戜懱惂偵憹愝偝傟丄懠偺恾彂娰偺慿媦擖椡偺廀梫偵傕墳偊傜傟傞懱惂傪峏偵嫮壔偡傞偙偲偵側偭偨丅 堦曽丄憗戝偺慿媦帠嬈偱偼婎杮偲偡傋偒J/MARC僨乕僞偺晄惍崌傪廋惓偟丄J/MARC偵側偄崁栚傕捛壛偟偰傾僋僙僗億僀儞僩傪憹傗偡搘椡傪偟偰偒偰偄傞丅嵟嬤傑偱懡偔偺恾彂娰偱偼J/MARC偑擔杮偱偺昗弨揑側MARC偲偟偰偺擣幆偑側偝傟偰偒偨偑丄偙傟偵偮偄偰偼夵慞偝傟傞傋偒栤戣揰偑悢懡偔巆偭偰偄傞丅変乆偼憗戝偱棙梡偝傟傞惛搙偺崅偄榓彂僨乕僞傪嶌惉偡傞偙偲偼摉慠偱偁傞偑丄憗戝偲嫟摨偱偙偺僨乕僞傪懠偺懡偔偺恾彂娰偵傕採嫙偟丄昡壙傪庴偗側偑傜偙傟傜偺栤戣揰傪堦偮堦偮夝寛偟偰丄杮摉偺堄枴偱偺昗弨揑側僨乕僞儀乕僗傪嶌傝忋偘偰備偒偨偄偲峫偊偰偄傞丅 変乆偺摑堦彂帍僨乕僞儀乕僗峔抸偺柌偼傑偩傑偩搑偵偮偄偨偽偐傝偱偁傞丅 恾彂娰儂乕儉儁乕僕傊 Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |