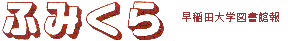 No.27(1990.12.15)p 5-7 No.27(1990.12.15)p 5-7
「衣笠詩文庫」の特色
紅野敏郎(教育学部教授・図書館参与)
「衣笠詩文庫」について語りたいと思います。この文庫の目録は、昭和38年8月、大野実雄さんの図書館長時代に作製されました。大野さんは「宝石のように愛蔵された詩集」と題され、巻頭に一文を寄せておられます。元ミツワ石鹸丸美屋副社長衣笠静雄氏(明治28〜昭和37)の愛蔵書であったのを、同夫人愛氏、令息和夫氏および長島健氏の御厚意により、大学図書館に寄贈されたものです。衣笠氏は理工学部の出身、こういうかたが仕事のあいまを縫って明治・大正・昭和三代にわたってのさまざまな詩集を収集されました。鈴木重三郎さんの「社会文庫」(日本近代文学館寄贈)にしても、多忙な政治家仕事のあいまを縫っての収集です。
「衣笠詩文庫」の特色は、超特別に珍しい詩集ばかりというのではなく、むしろ近代詩の歴史の裾野にあるような詩集をも網羅的に集められている、という点にあります。山宮充氏の著名な『明治大正詩書総覧』は、その領域では必要不可欠の書物ですが、図録の大部分は「衣笠氏蔵」となっています。この一点からでも、衣笠氏の集められた詩集の特殊性が十分にうかがえます。実業人の早稲田の先輩の人たち、そういう人の集められたものが、御遺族の御厚意で図書館寄贈となり、便利な目録が作られたこと自体、まことにありがたいことです。
頂点の本と裾野の本、これが同時に同居している風景、そこに近代詩研究の基本の姿が読みとれます。頂点の本でも、初版だけではなく、さまざまな重版も集められています。たとえば、薄田泣菫の『暮笛集』を眺めてみると、大阪の金尾文淵堂刊行の初版(明治32年11月)、2版(明治33年5月)、3版(明治39年5月)、いずれもそろっています。しかしその三種とも表紙が変わっています。表紙の意匠そのものを見ているだけでも時代の匂いが漂ってきます。詩集にはとくにそういう細部への注意が必要です。表紙のみではなく、内容も若干異なっています。従って泣菫全集を完全に編もうとすれば、おのずと各版の『暮笛集』が必要、ということになり、「衣笠詩文庫」のお世話にならねばならぬことになります。土井晩翠の博文館刊行の『天地有情』、これも有名な本ですが、『衣笠詩文庫』には、
| 初版(明治32年4月) |
|
| 2版(明治32年5月) |
3版(明治32年7月) |
| 8版(明治34年12月) |
26版(明治41年10月) |
| 35版(明治44年6月) |
37版(明治45年3月) |
| 38版(明治45年7月) |
39版(大正元年10月) |
| 59版(大正6年11月 |
71版(大正10年11月) |
| 76版(大正13年3月) |
81版(昭和5年一月) |
というように各種の本があります。表紙の意匠はほぼ同じですが、色が若干異なりますし、まあ版を重ねるに従って、広告の類も異なるし、同時代の批評も加わってきます。詩集などの場合、一冊で結構、というわけには決していかぬことがこれでわかってきます。
裾野の例でいきますと、 瀧沢秋暁の『有明月』(明治33年8月)という本があります。内外出版協会からの刊行、川上五平の編集によるものです。この
瀧沢秋暁という人は今日ではほとんど忘れられているようですが、信州の人で、「文庫」派の詩人・評論家として、明治30年代には活躍した人です。何年か前に遺族の手によって一巻本の『瀧沢秋暁著作集』が出されましたが、この時代のことを専門にしている人でも、
瀧沢秋暁に言及している人はあまり見かけません。この著作集については「信濃毎日」に頼まれ、秋暁に意義づけを含めた一文を草したことがありました。しかしそのときは、この『有明月』は実物を見ませんでしたが、「衣笠詩文庫」には適切に収められていたのです。古書展でもこの『有明月』はめったに出ない珍本です。藤村の詩集、あるいは泣菫や晩翠の詩集とともに、「文庫」派の
瀧沢秋暁にも目を向けることが、時代をよりいっそう立体的に把握できるのです。秋暁は、のち詩人としての仕事を放擲、家業にいそしみますが、佐藤春夫が佐久地方に疎開していた頃、この秋暁の家を訪れ、「秋和の里」という詩を作っています。佐藤春夫の心の中に、この瀧沢秋暁は深く根をおろしていたのです。秋暁と春夫は、直接には結びつかないにしても、この二人のかかわりは貴重、従って秋暁の存在を無視することは慎まねばなりません。
岩波書店版『白秋全集』の推進をしていたとき、白秋周辺の詩人として矢部季(季継)の存在がつねに気になっていました。遺族の隆太郎さんの協力も得たりしましたが、矢部の詩集『香炎草』(大正9年6月)がどうしても見つかりません。ところが「衣笠詩文庫」にそれが収まっていました。巡礼詩社の刊行として出ています。「矢部季」と通常言っていたのですが、「矢部季継」が本名ということもわかりました。こういう裾野の部分が実にこまかく収集されていて、助かることまことに甚大。実篤と日向の「新しき村」にともに住みついた武者小路房子の薔薇社刊行の唯一の詩集『星』(昭和9年4月)も「衣笠詩文庫」にはあります。武者小路実篤の詩集は入手しやすいですが、房子のものは実に入手し難い。プロレタリア文学の領域でも、白須孝輔の詩集『ストライキ宣言』(昭和5年2月)も、紅玉堂書店刊行のものがなんと二部集められています。『ストライキ宣言』の詩集としての芸術的価値は、それほど高くはないのですが、この種のものがおびただしく刊行されたり、発禁になったりしていることをやはり押さえておく必要があります。「白樺」と縁の深い近藤栄一の無我山房刊行の『サマリヤの女』(大正6年9月)は、私も手もとに持っています。その近藤栄一はそれ一冊と思っていたのですが、次の『微風の歌』(大正15年6月)が精神社から出ていたことは「衣笠詩文庫」ではじめて知りました。『天井から降る哀しい音』や『そうかも知れない』など「命終三部作」の作家として知られている耕治人の出発は詩人としてであったのですが、その耕治人の使命社刊行の『耕治人詩集』(昭和5年10月)や地?社刊行の『水中の桑』(昭和13年3月)も「衣笠詩文庫」に収まっています。これも私は二冊とも手もとに持っていますが、今日ではなかなか入手し難い本です。木山捷平の抒情詩社刊行の詩集『野』(昭和4年5月)、天平書院刊行の『メクラとチンバ』(昭和6年6月)も収まっているのには驚きました。小説家木山捷平の原点ともいうべき詩集で、ときどき古書展に出ますが、驚くほどの高い値がついています。紙質も悪く、薄くて、装幀もあまりよくない本ですが、内容はすばらしいものです。黄瀛の私家版の『景星』(1930年6月)、ボン書房刊行の『瑞枝』(昭和9年5月)なども、内容の検討と同時に、草野心平などとの関係をつきつめていく重要な詩集です。坂本瞭の『たんぽぽ』(昭和2年9月)まであるのにも驚きました。
 |
| 袂の形をした「片袖」与謝野鉄幹編 |
珍しいものとしては、与謝野鉄幹編の『片袖』三冊が目につきます。古書店の目録などでは写真版で大きく出ていて、非常に高い価がついています。その本の形は半月形に切れこんでいて、この変わった形が珍しいのです。ある人が「はじめきちんとなっていて、はさみで半月形に切ったのではないですか」といったのですが、そうではなく、はじめから表紙は半月形、つまり、片袖、袖の形のようになっているのです。これは内容そのもよりも、装幀の歴史の上で、珍しいし、また手にとってみますと、楽しい感じがするものなのです。いわゆる「眼福」というものです。第一集は完本ですが、残念ながら二集、三集は表紙のみが欠けています。マイクロフィッシュ化にあたっては、東京女子大学所蔵のものが三冊完本であったので、表紙のみはその協力を得ました。
相馬御風『御風詩集』もあれば、吉田一穂の『海の聖母』もあるし、最近亡くなられた吉岡実の第一詩集『静物』もあります。吉野臥城の仙台の尚文館刊行の『野茨集』(明治35年2月)、警醒社刊行の『小百合集』(明治35年7月)などはこれから再検討される本です。山本露滴の遺稿集は私も持っていますが、彼の美術評論社刊行の詩集『金盃』(明治41年7月)などはこの「衣笠詩文庫」ではじめて見ることが出来ました。山本露滴も明治文学史上の重要な裾野の一人です。
図書館ホームページへ
Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved.
Archived Web, 2002
| 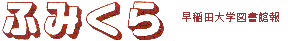 No.27(1990.12.15)p 5-7
No.27(1990.12.15)p 5-7