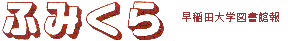 No.28(1991.2.1)p 11-14 No.28(1991.2.1)p 11-14
早稲田大学図書館を構成する、様々な調度に刻まれた紋様は、八芒星(八つの光芒がある星形)・八角形を基としていることをご存じでしょうか。まず正門大扉です(写真1)。彫金の透しに描かれているのは、星、鳥、貝、雲水、太陽を内に包みこむ唐草などです。まさに、八芒星の中に、ひとつの小宇宙が構築されているようです。ひと時、たたずむ者は、そこに吸い込まれてゆくような気分になります。本図書館の設計に携わった、故今井兼次先生は、この扉について、次のように述べられています。
この「図書館の顔」である正面大扉の次に挙げておきたいのは、大閲覧室にありました、銅製のシャンデリアです(写真2)。これも八芒星の形をしています。このシャンデリアは、昭和三十年代末から四十年代初め頃に取り外されてしまいました。昭和42年9月10日付の『早稲田キャンパス』(早稲田キャンパス新聞会編集)という新聞に、“図書館、20号館など改装”という見出しで、「第一閲覧室に取り外し可能の20ワットの蛍光灯が、一座席に一本ずつ取り付けられた、照明度は基準の五〇〇ルクスを上まわる一二〇〇ルクスとなった」として、一連の図書館改装工事の模様が伝えられています。大閲覧室が、より快適に、明るくなった一方で、せっかくのシャンデリアを蛍光灯に代えてしまったことを、惜しむ声もあたようです。 確かに照明度は、閲覧者の方にとって、大きな問題であったと思います。しかし、光がともる八芒星は、図書館の建築意匠として、なくてはならないものであったに違いありません。その八芒星のシャンデリアの名残として、それを吊ってあった天井部分は、現在でも八芒星の形をとどめています(写真3)。 そのほかに、床タイル、階段の透し、第二閲覧室の扉の破風、さらに学生入口脇の常夜灯など、八芒星もしくは八角形をした意匠は、そこかしこに見い出されます(写真4〜8) 以上のように八芒星によって、図書館を象徴しようとした建築家の企図は明らかです。研究者の方々にとっては学問の場であり、館員にとっては仕事・生活の場である2号図書館は、実に豊かな意匠に満ちていることを、惜別の念をこめてあらためて銘記しておきたいと思います。 ちなみに、キリスト教国において、八は、天地創造の七日間とキリストの復活日を示し、マタイ伝には、「八つの至福の教え」が説かれています。また、正方形(この世)と円(永遠)との間を表し、八角形は中間図形で、円の面積を求める永遠の難問を解く方法の一つであるとされています(註2)。 この図書館が今井兼次先生の処女作であること、そして心身を包みこむような限り無い空間のやわらかさをたたえた建築であることに、私は誇りと、そして何よりも安らぎをおぼえます。 註1)『旅路』(彰国社 1967)より。 註2)アト・ド・フリース著『イメージ・シンボル事典』(大修館書店 1984)“Eight”の項より。 写真1、3、4〜8.撮影=小野田照子。 写真2.『現代日本建築家全集5.今井兼次、武基雄』(三一書房 1971.9)p.105 【その他の参考資料】 ・中村鎭「早稲田大學圖書館の建築−最も優れたる建築製作態度の或種のものに就て−」(『中央美術』1926年6月号) ・今井兼次著『建築とニューマニティ』(早稲田大学出版部 1985再刊)ほか
Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |
|||||||||||||






 (左)写真7 床タイル
(左)写真7 床タイル