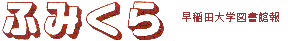 No.32(1991.10.25)p 2 No.32(1991.10.25)p 2
川 勝 平 太(政治経済学部教授・図書館副館長) 文学は、刻印、記載、写植されている材料から独立しては存在しない。材料は大昔には亀甲や獣骨であったが、それが石や銅に移り、さらに木、竹、布と変遷し、そして紙に変わった。製紙法が発明されたのは105年頃といわれている。以来、紙は文化隆盛の基となった。 唐代の文運を支えたのは木版印刷術であり、中国の製紙法は、東方へ朝鮮をへて7世紀に日本に伝わり平安期文学を生み、西方へは8世紀に中東に伝わり、いわゆるサマルカンド紙が羊皮やパピルスにとってかわってアラビア文化の隆盛をもたらした。下って12世紀にはスペインに伝わり、15世紀に活字印刷術が発明されて、それがギリシャ・ローマ古典の大々的な復興を可能にしたのである。H・G・ウェルズがキリスト教諸国に紙が伝わったことを重視して「ヨーロッパの知的復興を可能にしたのは紙だ」(『世界史概観』)と断言したのは誇張ではない。文学は紙という最高の恋人を見い出し、その幸せな関係は永遠に続くかにみえた。人間にとって、文字への渇望が紙への愛着と不可分になったのは文化史の必然の成り行きである。 印刷物への大量需要が生まれたヨーロッパにおいては18世紀末に機械製紙法が発明され、翌世紀には大量生産が可能になった。紙の材料に木材パルプが用いられ実用化されたのは19世紀中葉であった。すでに江戸期に世界最高水準の識字率をもっていた日本人が、この新しい機械製紙技術をただちに導入したのは、けだし、当然である。早くも明治5年に機械製糸工場が出来ている。だが、素材をパルプにした結果、今日の深刻な酸性紙問題を胚胎させることになった。 マイクロ化事業は、文学情報を酸性紙の劣化による喪失から防ぎ、マイクロ・フィルムやフィッシュで残す試みである。これまで、世界の文化を飛躍的に発達させてきたのは文字と紙とのセットであった。文字と紙との幸せなカップルは、離婚することはあるまいが、マイクロ化により、別居を余儀なくされる。それは文字と人間の付き合いの仕方を変えていくであろう。かならずしも良い方向ばかりではない。 マイクロフィルムを使って仕事をすると、心身の疲れがひどい。それだけに書籍への愛着はたちがたい。かつてインドにアジアで最初に結成された紡績連合会の年次報告書を調べに行ったことがある。これは19世紀末のイギリスとインドとの深刻な貿易摩擦、さらに明治日本とインドとの経済競争の実態をしらせる資料で、当時の国際経済を研究する上では欠かせないものだ。資料はボンベイだけにあり、他の地域のものは散逸した。それがぞんざいに管理され、頁を繰るごとにボロボロと紙が砕けていくのを眼前にしたとき、胸中に走った止めどない嘆きは忘れえない。明治期本が劣化していくのをみるのは哀しい。だが文字情報を失えば、それにまさる悲しみを生む。マイクロ化事業を支えているのは危機感であり、文字への愛着であり、文化継承の使命感である。ご支援をお願いしたい。 Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |