|
 |
| パネルディスカッション |
 |
|
宗像和重(早稲田大学図書館副館長):日本語および英語で行われますので、もう一度イヤフォンについてご説明を申し上げます。お願いします。
アナウンス:受付でお渡しした同時通訳用イヤフォンの差込口は、座席左の肘掛けの内側にあります。そこにプラグを差し込んでいただいて、チャンネルをお選びください。チャンネル1が日本語の通訳、チャンネル2が英語の通訳が流れます。
宗像和重(早稲田大学図書館副館長):ありがとうございます。会場の皆様には、必要に応じてイヤフォン等をお使いいただきますようお願いします。それでは内海先生、シンポジウムの先生方、どうぞよろしくお願いします。
アナウンス:パネリストの皆さまにご案内申し上げます。ステージ上のイヤフォンは0が日本語、1が英語です。また、ボリュームが0になっていますので、上げてお使いください。
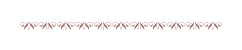
 |
内海孝(東京外国語大学教授):それでは後半のメインになりますが、パネルディスカッションという形で始めさせていただきます。今、ド・バリー先生と甲斐美和さんのお話を受けた形で、もう一度ドナルド・キーンさんに、午前中にお話になった内容とはまた違う形で、新しい思いが込み上げてきたと思いますので、その辺からお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。 |
|  |
 |
ドナルド・キーン(コロンビア大学名誉教授):何と言いましょうか。私たちはどちらかというと一緒に冒険をしていました。つまり、戦後になったらもう誰も日本語に興味がなかったのです。もう日本語はダメだ、日本が立ち直るには少なくとも50年かかるだろうという常識がありました。途中で、日本がダメだったら中国に切り替えるという人もいましたし、ほかの日本とまったく関係のない勉強に移った人も多かったです。戦時中、海軍の日本語学校でたぶん卒業生は2000人以上いましたが、戦後になっても日本研究を続けた人はたぶん30名もいなかったでしょう。つまり、絶望的な勉強だと。
しかし、どうしてもやりたい人がいました。ド・バリーさんも私もそうでした。仮に飢え死にしても構わないから、どうしてもその勉強を続けたいと。どうなるかわからなかったです。私の場合は、アメリカでは就職できなかったですが、英国でできました。ケンブリッジ大学という大変立派な大学で教えるようになりました。ド・バリーさんはコロンビア大学に就職しました。彼はそのときからアジア、日本、中国、インド、3つの文化のあらゆる文献を調べるべきだと。西洋の場合はそういう本がありました。『西洋思想の源泉』などがありましたが、東洋のものはまったくありませんで、それらしい本もありませんでした。ド・バリーさんはちょうど先生の講義を基にして日本の本を先にやるでしょう。つまり、インドが一番ヨーロッパに近く、言葉もヨーロッパの系統ですが、しかし一番遠い、扱いにくい国です。日本は一番近く感じました。日本からやりだしました。次は中国、最後はインドになりました。そういう本ができた頃は、果たしてどのくらい読まれるかわからなかったです。ところが、コロンビア大学出版部から出た本で一番のベストセラーです。つまり世界中でそれが使用されています。例えば、イタリアで日本研究をしようと思ったら、まず英語を知らなければ教えられません。それはドイツでも、北欧でも、メキシコでも同じことです。どうしてかというと、そういう本は英語でしかないからです。そのような背景があって、私はコロンビア大学に戻ってド・バリーさんと一緒に教えて、大変すばらしい冒険でした。
|
|